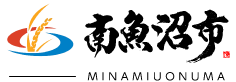掲載日:令和6年4月1日更新
年金の種類
次の年金を受け取ることができます
- 老齢基礎年金:老後の備えに
- 障がい基礎年金:病気やケガで障がいが残ったら
- 遺族基礎年金:もしも、家の働き手に先立たれたら
第1号被保険者の独自給付
- 寡婦年金
- 死亡一時金
老齢基礎年金…老後の備えに
受給要件
保険料を納めた期間(第2号・第3号被保険者期間を含む)や免除期間などを合わせて10年以上ある人が、65歳になった月の翌月分から年金を受け取ることができます。
繰上げ支給と繰下げ支給
老齢基礎年金を受給できるのは65歳からですが、希望により60歳以降であれば繰り上げて受給することができます。年金額は、年金を受給しようとする年齢で減額されます。(繰上げ支給)
また、66歳以降70歳まで繰下げて、増額された年金を受給することもできます。(繰下げ支給)
年金額
20歳から60歳になるまでの40年間の納付月数などに応じて年金額が計算されます。
未納や免除の期間があると減額されます。詳しくは、日本年金機構ウェブサイトで確認してください。
関連リンク
障がい基礎年金…病気やケガで障がいが残ったら
受給要件
- 初診日に国民年金の被保険者期間中であるか、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で、以前に被保険者であった人
- 障がい認定日に、1級または2級の障がいの程度にある人
- 国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間が、初診日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上であること。または、初診日が令和8年4月1日以前で、初診日に65歳未満の場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間の保険料を納付していること。
障がい認定日とは:障がいのもととなった病気やケガで、初めて医師の診断を受けた日(初診日)から1年6か月たった日、または1年6か月たたない間に治った日(症状が固定した日)
20歳前に初診日がある病気やケガの場合
20歳前に初診日がある場合には、20歳になったとき(障がい認定日が20歳以後のときは、障がい認定日)に障がい等級1級、または2級の程度にあるとき
ただし、本人に一定の額を超える所得があるときは、支給が停止されます。
年金額
障がいの状態により1級、または2級の年金を受け取ることができます。
生計を維持されている子があるときは、子の加算額を受け取ることができます。(18歳に達する日の属する年度末までの間にある子か、20歳未満で1級、または2級の障がいの状態にある子)
詳しくは、日本年金機構ウェブサイトで確認してください。
関連リンク
遺族基礎年金…もしも、家の働き手に先立たれたら
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子が受け取ることができます。(子は18歳に達する日の属する年度末にある子か、20歳未満で1級または2級の障がいの状態にある子)
支給要件
- 国民年金の被保険者が死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき
ただし、1と2の場合、死亡日前に一定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。
保険料納付用件
国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間が、死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上であること。
年金額
遺族年金は亡くなられた月の翌月分から受け取ることができます。
詳しくは、日本年金機構ウェブサイトで確認してください。
関連リンク
第1号被保険者の独自給付
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含むが若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を除く)が25年以上ある夫が死亡したとき、妻が60歳から65歳になるまでの間に受給できます。ただし、夫との婚姻期間が10年以上あること、夫が障がい基礎年金や老齢基礎年金を受けていないことが条件となります。
年金額
夫が受けられるはずの老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納付した月数が36月(一部納付は月数が変わります)以上ある人で、老齢基礎年金・障がい基礎年金のいずれも受給せずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受給できない場合に受給できます。
支給される額
納付期間より120,000円~320,000円
関連リンク
厚生年金や共済組合期間のある人
厚生年金や共済組合期間のある人や、加入中の障がいや死亡の場合は厚生年金や共済組合から、老齢・障がい・遺族年金が基礎年金に上乗せ支給されます。