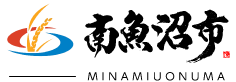掲載日:令和7年4月1日更新
障がいのある人もない人も、ともに生きる社会を目指して
この法律は障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も、ともに生きる社会をつくることをめざし、平成28年4月に施行されました。
対象となる障がい者は
障害者手帳を持つ人だけではなく、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、そのほか心身の機能に障がいがあり、障がいや社会の中にある障壁によって日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人
不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供
障がい者差別解消法では「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
不当な差別的取り扱いと合理的配慮の提供について
| 国の行政機関・地方公共団体など | 民間企業など | |
| 不当な差別的取り扱い | 禁止 | 禁止 |
| 合理的配慮 | 法的義務 |
法的義務 |
- 合理的配慮はお金がかかる場合もあります。その場合は他の工夫ややり方を考えることになります。
- 個人事業者やNPO法人なども民間企業に含みます。
- 民間企業の合理的配慮については「努力義務」から「義務」へ改正されました。(令和6年4月1日)
不当な差別的取り扱いとは
正当な理由なく障がいがあるという理由だけでサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けるような行為
具体例
- 「障がいがある」という理由だけでスポーツクラブに入れてもらえない
- 「障がいがある」という理由だけでアパートを貸してもらえない
- お店に入ろうとしたら、車いすを利用しているという理由で断られた
合理的配慮とは
障がいのある人が困っている時に、その人の障がいに合った必要な手助けや方法を相手に伝えて、負担とならない範囲で「社会的障壁」を取り除くために個別の状況に応じて行われる配慮のこと
具体例
- 車いすの人がお店を利用する時に手助けをする
- 耳の不自由な人に筆談で説明する
- 目の不自由な人に読み上げて説明する
社会的障壁とは
障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもので、次のようなものです
- 社会における事物(利用しにくい施設や設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習・文化など)
- 概念(障がいのある人への偏見など)
具体例
- 道路の段差:3センチメートル程度の段差でも、車いすで進めなくなります
- 書類:難しい漢字ばかりだと理解しずらい人もいます