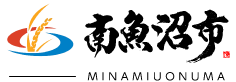掲載日:令和6年6月18日更新
所得控除とは、配偶者や扶養親族の有無など、納税者ひとりひとりの事情に応じて税金を負担していただくために、所得金額から差し引くものです。各控除による所得税の還付は市・県民税の申告では受けられません。所得税の確定申告が必要です。
所得控除の種類は以下のとおりです。
医療費控除
従来の医療費控除の概要
申告者や生計を一にする配偶者その他親族のために前年中に支払った医療費がある場合の控除
控除額
前年中に支払った医療費(保険金などによる補てん額を差し引いた後の金額)から下記のいずれか少ないほうの金額を控除した金額(最高200万円)
- 総所得金額等の5パーセント
- 10万円
申告の注意
- セルフメディケーション税制を受ける人は、従来の医療費控除は適用できません
- 控除を受けるには医療費控除の明細書が必要です
セルフメディケーション税制の概要(医療費控除の特例)
申告者が健康の保持増進と疾病の予防として一定の取組を行い、申告者や生計を一にする配偶者その他の親族のために前年中に支払った特定の医薬品の購入費が1万2千円を超える場合の控除
特定の医薬品とは、医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。特定の医薬品は、厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
健康の保持増進や疾病の予防としての一定の取組
| 一定の取組 | 証明書など |
|---|---|
| 特定健康検査(メタボ検査など) | 特定健康診断という名称または保険者名(加入医療保険名)が記載された領収書または結果通知表 |
| 予防接種(インフルエンザなど) |
領収書または予防接種済証 (注)新型コロナウイルスワクチンは対象外です |
| 定期健康診断(事業主検診) | 定期健康診断という名称または勤務先名称が記載された結果通知表 |
| 健康診査(人間ドックなど) | 保険者名などの記載がある結果通知表 |
| がん検診 | 領収書または結果通知表 |
控除額
前年中の特定の医薬品の購入費から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)
申告の注意
- 従来の医療費控除を受ける人は、セルフメディケーション税制は適用できません
- 控除を受けるにはセルフメディケーション税制の明細書が必要です
社会保険料控除
控除の概要
申告者や生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料(健康保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、農業者年金保険料、厚生年金保険料など)を支払ったり、給与などから天引きされた保険料がある場合の控除
控除額
支払保険料の合計額
申告の注意
- 国民年金保険料や国民年金基金の掛金については、領収書または支払証明書が必要です
- 生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から引落し(特別徴収)されている保険料は申告者の控除の対象になりません
- 生計を一にする配偶者その他親族の国民健康保険税や後期高齢者医療保険などを申告者が口座振替により支払った場合には、申告者の控除の対象になります
小規模企業共済等掛金控除
控除の概要
小規模企業共済法に規定された共済契約(旧第二種共済契約を除く)に基づく掛金や、確定拠出型年金法の企業型年金加入者掛金や個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済掛金を支払った場合の控除
控除額
支払掛金の合計額
申告の注意
控除を受けるには領収書または支払証明書の提示が必要です
生命保険料控除
控除の概要
新(旧)生命保険、新(旧)個人年金保険、介護医療保険で、申告者が支払った保険料がある場合の控除
控除額
新契約、旧契約、新契約と旧契約の両方に基づく控除額の合計額(最高7万円)
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約など)に基づく控除額
新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
| 支払額保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 12,001円以上32,000円以下 | |
| 32,001円以上56,000円以下 | 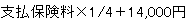 |
| 56,001円以上 | 28,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約など)に基づく控除額
旧契約に基づく旧生命保険料、旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
| 支払額保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 15,001円以上40,000円以下 | |
| 40,001円以上70,000円以下 | |
| 70,001円以上 | 35,000円 |
新契約と旧契約の両方の支払保険料がある場合の控除額
- 旧生命保険料または旧個人年金保険料の支払保険料が4万2千円以下の場合
新契約と旧契約で計算した金額の合計額(最高2万8千円) - 旧生命保険料または旧個人年金保険料の支払保険料が4万2千円を超える場合
旧契約で計算した金額(最高3万5千円)
地震保険料控除
控除の概要
損害保険契約等について、申告者が支払った地震等損害部分の保険料がある場合の控除
注意:平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(保険期間や共済期間が10年以上で、満期返戻金を支払う旨の特約があり、かつ、平成19年1月1日以降契約の変更をしていないものなど)について、申告者が支払った保険料(旧長期損害保険料)がある場合を含みます
控除額
地震保険料控除、旧長期損害保険料に基づく控除額の合計額(最高2万5千円)
地震保険料に基づく控除額
| 支払額保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 50,000円以下 | 支払保険料の半額 |
| 50,001円以上 | 25,000円 |
旧長期損害保険料に基づく控除額
| 支払額保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 5,001円以上15,000円以下 | |
| 15,001円以上 | 10,000円 |
地震保険料と旧長期損害保険料の両方の支払保険料がある場合の控除額
地震保険料、旧長期損害保険料で計算した金額の合計額(最高2万5千円)
申告の注意
- 控除を受けるには控除証明書の提示が必要です
- 一つの契約で地震保険料と旧長期損害保険料の両方が対象となる場合は、選択によりどちらか一方しか控除を受けることができません
障害者控除
控除の概要
申告者、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満の扶養親族を含みます)が障害者や特別障害者である場合の控除
控除額
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 障害者 | 26万円 |
| 特別障害者 | 30万円 |
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 障害者 | 26万円 |
| 特別障害者 | 30万円 |
| 同居特別障害者 | 53万円 |
寡婦(寡夫)・ひとり親控除
控除の概要(令和3年度(令和2年分)以降)
申告者が寡婦またはひとり親である場合の控除
寡婦と控除額
下記の「ひとり親」に当たらない人で、次の1から3のいずれにも当てはまる人
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 下記のいずれかに該当すること
夫と死別した後婚姻をしていない人または夫が生死不明の人
夫と離別した後婚姻をしていない人で、扶養親族を有する人 - 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
控除額:26万円
ひとり親と控除額
現に婚姻していない人または配偶者が生死不明の人で、次の1から3のいずれにも当てはまる人
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいること
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
控除額:30万円
控除の概要(令和2年度(令和元年分)以前)
申告者が寡婦または寡夫である場合の控除
寡婦の区分と控除額
- 夫と死別・離婚した後再婚していない人や夫が生死不明の人で、扶養親族や総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある人:26万円
- 上記に該当する人で、扶養親族である子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人:30万円
- 夫と死別した後再婚していない人や夫が生死不明の人で、合計所得金額が500万円以下の人:26万円
寡夫の区分と控除額
- 妻と死別または離婚した後再婚していない人や妻が生死不明の人で、合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある人:26万円
勤労学生控除
控除の概要
次のいずれにも該当する場合の控除
- 給与所得などの勤労による所得があること
- 合計所得金額が75万円以下(令和2年度(令和元年分)以前は65万円以下)で、1.の勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
- 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校などの特定の学校の学生、生徒であること
控除額
26万円
配偶者(特別)控除
控除の概要
申告者に生計を一にする配偶者がいる場合に、申告者と配偶者のそれぞれの前年中の合計所得金額に応じて受けられる控除
配偶者控除
配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和2年度(令和元年分)以前は38万円以下)の場合に次の表により控除額を求めます。
| 配偶者の年齢 |
申告者の合計所得金額 |
申告者の合計所得金額 |
申告者の合計所得金額 950万円超1000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 70歳未満 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
|
70歳以上 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に次の表により控除額を求めます。
令和2年度(令和元年分)以前は配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下の場合に配偶者特別控除が適用できます。次の表の配偶者の合計所得金額の各項目を10万円ずつ減額した範囲に当たるものが対象で、控除額は変わりません。
| 配偶者の 合計所得金額 |
申告者の合計所得金額 |
申告者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
申告者の合計所得金額 950万円超1000万円以下 |
|---|---|---|---|
| 48万円超 100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
|
100万円超 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
申告の注意
- 申告者の前年中の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者(特別)控除を受けられません
- 配偶者が事業専従者となっている場合は、配偶者(特別)控除を受けられません
- 夫婦間でお互いに配偶者特別控除を適用することはできません
扶養控除
控除の概要
申告者に合計所得金額が48万円以下(令和2年度(令和元年分)以前は38万円以下)の控除対象扶養親族となる人がいる場合の控除
控除額
| 扶養親族区分 | 控除額 |
|---|---|
| 年少扶養親族(16歳未満) | 0円(適用なし) |
| 一般扶養親族(16歳以上19歳未満と23歳以上70歳未満) | 33万円 |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 45万円 |
| 同居老親等の老人扶養親族(70歳以上) 注意:同居老親等とは、申告者や配偶者の直系尊属で、申告者や配偶者との同居を常としている人をいいます |
45万円 |
| 同居老親等以外の老人扶養親族(70歳以上) | 38万円 |
申告の注意
- 16歳未満の扶養親族(年少扶養)の扶養控除額は0円ですが、市・県民税の非課税限度額の判定における扶養親族数では考慮されます
基礎控除
控除の概要(令和3年度(令和2年分)以降)
申告者の合計所得金額が2,500万円以下の場合に適用される控除
控除額
| 申告者の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 0円(適用なし) |
控除の概要(令和2年度(令和元年分)以前)
すべての人に適用される控除
控除額
33万円
雑損控除
控除の概要
下記のいずれかに該当する場合の控除
- 申告者や、総所得金額等が48万円以下(令和2年度(令和元年分)以前は38万円以下)の生計を一にする配偶者その他の親族が、災害や盗難などで住宅や家財などに損害を受けた場合
- 災害などに関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした人
控除額
下記のいずれか大きいほうの金額
- 損失額(保険金などによる補てん額を差し引き後)から総所得金額などの10パーセントを控除した金額
- 5万円を超える災害関連支出の金額
申告の注意
- 控除を受けるには領収書が必要です